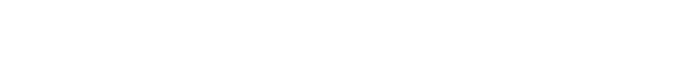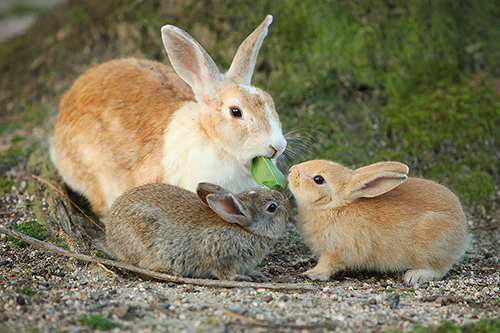愛犬のてんかん症状を徹底解説!飼い主が知っておくべきポイント
2025年3月20日

—————————————————————
監修:わんにゃん保健室 獣医師 江本 宏平
https://asakusa12.com
—————————————————————
愛犬がてんかんを発症したら、飼い主は突然のことで戸惑うことでしょう。突然の異常な行動に気づいても、どう対処してよいかわからないかもしれません。このブログでは、犬のてんかんについての基本的な知識から、発作時の対処法、さらにはリスクの高い犬種まで、てんかんに関する幅広い情報を提供します。愛犬のてんかんへの理解を深め、適切な対応ができるようになりましょう。
目次
- 1. 愛犬のてんかんって何?症状の基本を理解しよう
- てんかんの基本的な症状
- その他の症状
- 注意点
- 2. てんかん発作の主な症状と見分け方
- 焦点性発作の症状
- 全般発作の症状
- 発作の前兆と発作後の行動
- 3. 要注意!てんかんが起きやすい犬種とリスク
- てんかんのリスクが高い犬種
- 発作を引き起こしやすい環境
- 飼い主が意識すべきポイント
- 4. てんかん発作の原因と種類を詳しく解説
- てんかんの原因
- てんかんの種類
- 発作の分類
- 5. 発作が起きたときの正しい対処法と注意点
- 発作中の行動
- 発作後の対応
- 注意点
- まとめ
- よくある質問
- 1. 犬のてんかんの症状はどのようなものですか?
- 2. 発作の前兆や後遺症はどのようなものですか?
- 3. てんかんが起きやすい犬種はどのようなものですか?
- 4. 発作が起きた際にはどのように対応すべきですか?
1. 愛犬のてんかんって何?症状の基本を理解しよう
犬のてんかんは、脳における異常な神経活動が原因で起こる疾患であり、飼い主にとっては見慣れない変化を引き起こすため、非常に心配なものです。特に愛犬が突然けいれんを起こすと、飼い主はどう対応すべきか戸惑うことが多いでしょう。まずはてんかんの基本的な症状を理解することが重要です。
てんかんの基本的な症状
犬のてんかんは、発作の種類によって症状が異なります。主に以下のような全身発作と部分発作の二つに分類されます。
全身発作
全身発作は、脳全体に異常な信号が伝達されることから起こるもので、以下の症状が見られます。
- ・けいれん:全身の筋肉が硬直し、激しく振る。
- ・意識喪失:多くの場合、犬は意識を失い、周囲の状況が認識できなくなる。
- ・体の硬直:全身が不自然に硬くなることがあり、時にはけいれんの間に呼吸が困難になることも。
部分発作
部分発作は、脳の一部で異常が起こるため、症状が限定的です。以下のような症状が見られます。
- ・体の一部分のけいれん:例えば、顔や後ろ足が突然引きつることがある。
- ・焦点が合わない:目が虚ろになり、周囲を見ても反応が鈍い。
- ・口をぱくぱくさせる:チューインガム発作とも呼ばれ、無意識に咀嚼する動作を繰り返すことがある。
その他の症状
てんかんの発作を伴う犬は、以下のような症状も示すことがあります。
- ・急な倒れ込み:何の前触れもなく倒れてしまうことがある。
- ・ヨダレ:大量のよだれが出ることもあります。
- ・不安や落ち着きのなさ:発作の前に、犬がソワソワしたり、落ち着かなかったりする場合があります。
注意点
まず、一回の発作が即てんかんの診断に繋がるわけではありません。数回の発作が見られなければ、その可能性は低いと考えられています。しかし、発作が一度でも起きた際には、速やかに動物病院で見てもらうことが非常に重要です。特に、3回以上の発作が短期間に見られる場合は、特に注意が必要です。
以上のように、愛犬のてんかん症状を理解することで、飼い主として適切に対応するための第一歩を踏み出すことができます。病気の可能性を早期に発見し、適切な治療を施すことで、愛犬の健康を守ることができます。

2. てんかん発作の主な症状と見分け方
犬のてんかん発作は、さまざまな形で現れるため、その症状を正確に把握することが重要です。発作の種類によって見られる症状は異なりますが、以下に主な症状をまとめます。
焦点性発作の症状
- ・落ち着きがない
犬は特に不安を感じたり、通常の行動パターンから外れた動きをすることがあります。 - ・部分的な筋肉の痙攣
顔の一部や四肢の筋肉が痙攣することが見られます。例えば、手足の小刻みなけいれんなどが典型的です。 - ・行動の異常
犬が自分の尻尾を追いかけたり、空中の何かを噛むような行動をすることがあります。これらは見逃しやすい兆候ですが、重要なサインとなり得ます。 - ・唾液の異常分泌
発作中に大量の唾液が出ることがあり、周囲が気づく手がかりになることもあります。
全般発作の症状
- ・意識の喪失
多くの場合、犬は意識を失い、発作の間は自分の周囲の状態を認識できません。 - ・全身の筋肉が硬直する
突然全身が硬直し、筋肉が緊張する様子が見られることがあります。 - ・全身の震え
手足がガクガク震えたり、犬かきのように手足を動かすことがあります。 - ・失禁や脱糞
発作中に体が制御できず、失禁や脱糞をする場合もあります。
発作の前兆と発作後の行動
前兆の症状
発作の前に見られる行動として、以下のような異常があります。
- ・攻撃的または不安定になる
性格が一時的に変わることがあり、攻撃的になることもあります。 - ・急な動きやウロウロする行動
何かに怯えたように、落ち着かない行動を示すことがあります。
発作後の症状
発作が終わった後も、異常が見られることがあります。
- ・よろよろした動き
立ち上がれずに体が不安定になることがしばしばあります。 - ・異常な食欲や飲水
食欲が異常に増したり、水をたくさん飲む行動が観察されることがあります。
犬のてんかん発作は非常に複雑で、一見しただけでは発作であると分からないこともあります。したがって、普段と異なる行動や症状に気づいた場合は、すぐに獣医師に相談することが重要です。特に発作が1日に何度も起こる場合や、発作が5分以上続く場合は緊急対応が必要です。

3. 要注意!てんかんが起きやすい犬種とリスク
てんかんはどの犬種にも発症する可能性がありますが、特に特発性てんかんが多く見られる犬種が存在します。これらの犬種は遺伝的な要因や、生活環境、ストレスなどの影響を受けやすいとされています。ここでは、てんかんが起きやすい犬種の一覧とそのリスクについて詳しく解説します。
てんかんのリスクが高い犬種
以下の犬種は、特にてんかんを発症しやすいとされています。これらの犬種を飼っている方は、日常的に観察し、異常を早期に発見することが大切です。
- ゴールデン・レトリーバー
- ラブラドール・レトリーバー
- ビーグル
- シェットランド・シープドッグ
- ボーダー・コリー
- プードル
- アメリカン・コッカー・スパニエル
- シベリアン・ハスキー
- バーニーズ・マウンテン・ドッグ
これらの犬種は、遺伝的な要因が強く関与していると考えられています。特に、ゴールデン・レトリーバーやラブラドール・レトリーバーは、日本で非常に人気がある犬種であり、そのため、飼い主は発作に対して注意を向ける必要があります。
発作を引き起こしやすい環境
てんかんは遺伝的な要因だけでなく、環境要因も影響します。以下のような状況が発作を引き起こすリスクがあるため、注意が必要です。
- ・ストレスの多い環境(大きな音や多くの人がいる場所)
- ・急激な気候変化(特に気圧の変化)
- ・運動不足(適度な運動を心がけることが重要)
- ・激しい興奮(遊びや他の犬との接触後の興奮状態)
飼い主が意識すべきポイント
愛犬が高リスクな犬種である場合、以下のポイントを意識することで、早期発見につなげることができます。
- ・日常的な観察:普段と様子が違った場合は注意深く観察しましょう。
- ・発作の兆候を記録:発作前や発作時の様子をメモしておくことで、獣医師に的確に伝えられます。
- ・ストレス管理:愛犬がストレスを感じやすい状況を理解し、その状況を避ける努力をしましょう。
このようにして、てんかんを持つ犬種に対する理解を深めることで、愛犬の健康を守る手助けとなるのです。日々の小さな観察と適切な対応が、愛犬の生活の質を維持するためには欠かせません。

4. てんかん発作の原因と種類を詳しく解説
犬におけるてんかんは、さまざまな要因に起因する脳の異常状態で、その発作に伴う症状や発生のメカニズムは犬種や環境によって異なります。これらの原因や種類を正確に理解することが重要です。本節では、犬のてんかんに関する基本的な知識を詳しく見ていきましょう。
てんかんの原因
犬におけるてんかん発作の原因は、大きく「構造的要因」と「非構造的要因」に分けられます。
構造的要因
- ・脳の外傷: 頭部の外的な衝撃や脳腫瘍などによる脳の異常は、発作を引き起こす重要な要因です。
- ・脳の炎症: 感染症による脳の炎症も、てんかん発作を引き起こす原因の一つとされています。
- ・血管の疾患: 脳卒中や血管の障害がある場合、一部の脳機能が損なわれ、てんかん発作を誘発することがあります。
これらの要因は、通常は後天的に発生し、遺伝的要因が影響することは少ないと考えられています。
非構造的要因
- ・特発性てんかん: 明確な構造的異常がなくても、遺伝的背景により発作が起こる状態です。これは多くの犬に見られます。
- ・環境要因: ストレス、不足な睡眠、過度の疲労は発作を誘発することがあります。特に大きな環境の変化や心理的なストレスに対しては犬が敏感です。
てんかんの種類
てんかんは「症候性てんかん」と「特発性てんかん」の2つに分けられます。
症候性てんかん
このタイプは、脳に明らかな異常が存在する場合に該当します。脳腫瘍や脳炎、特定の遺伝的異常があると、てんかん発作が二次的に引き起こされることが多いです。
特発性てんかん
特発性てんかんは、脳の構造に明確な異常が見られず、特定の原因がない状態です。つまり、外部の影響や疾患歴がなくても発作が発生します。このタイプは特定の犬種に多く、遺伝的要因が影響すると言われています。
発作の分類
てんかん発作は、症状に基づいて「焦点性発作」と「全般発作」に分けることができます。
焦点性発作
焦点性発作は脳の特定部分で異常な電気活動が起き、それに伴い筋肉のけいれんや異常行動が見られます。
全般発作
全般発作は脳全体で異常な電気活動が発生し、意識を失うことが多いです。全身の硬直やけいれんが特徴的です。
犬のてんかんについてしっかり理解することで、愛犬の健康を適切に管理し、発作が起きた際には速やかに対応することが可能になります。犬がてんかんを患っている場合、その意義を理解し、愛犬の健康と安全を守ることが非常に重要です。

5. 発作が起きたときの正しい対処法と注意点
犬がてんかん発作を起こした場合、その状況において冷静に対処することが非常に重要です。ここでは、発作発生時の正しい対処法と注意点について詳述します。
発作中の行動
- ・周囲の安全を確保する – 犬が発作を起こすと、周囲の物にぶつかる可能性があります。発作中は、周囲の障害物を取り除き、危険な物から犬を守りましょう。
- ・刺激を避ける – 大声を出さず、激しい動きも避けるように心がけます。犬が安心できる静かな環境を保つことが大切です。
- ・体の支えを行う – 発作中に犬が倒れる際は、硬い地面に頭をぶつけないよう、そっと柔らかいタオルやクッションを置いてあげると良いでしょう。
- ・発作の記録を取る – 発作がどれくらいの時間続いたのか、どのような症状が見られたのかを記録しましょう。後に動物病院を受診する際に、診断に役立ちます。
発作後の対応
- ・観察を続ける – 発作が治まった後も犬の様子を観察し、行動が正常に戻っているか確認します。このとき、犬が落ち着くまで静かに見守りましょう。
- ・体温の管理 – 特に短頭種の犬は体温の上昇に注意が必要です。体が熱を持っている場合は、涼しい場所に移動させたり、濡れたタオルを体にかけたりしてケアします。
- ・獣医師への相談 – 初めての発作や発作が長引く場合は、すぐに動物病院を受診する必要があります。特に、下記の症状が見られる場合は速やかに行動を起こしましょう。 – 発作が5分以上続く。 – 発作後すぐに次の発作が起こる。 – 意識が戻らない状態。
注意点
- ・急がず冷静に行動する
- 発作時の緊急性に焦って行動するのではなく、まずは冷静に犬の安全を確保し、必要な情報を記録することが重要です。
- ・薬の管理
- 獣医師から処方された薬を服用している場合は、指示通りの用法を守り、定期的に通院して血液検査などを受けるよう心がけます。
- ・環境の見直し
- 発作がどのようなタイミングで起こるのか、環境要因を観察し、予防策を考えることも必要です。ストレス要因を取り除く工夫をすることで、発作の頻度を減少させる助けとなるかもしれません。
これらの事柄を遵守することで、愛犬がてんかん発作を起こした際に、より良い対応ができるようになります。

まとめ
犬のてんかんは、飼い主にとって非常に心配な状況ですが、正しい知識と適切な対応をすることで、愛犬の健康を守ることができます。発作の種類や原因、症状の特徴を理解し、発作時の対処法を身につけることが大切です。また、発作を引き起こしやすい環境要因を把握し、予防策を講じることも重要です。定期的な検査と、獣医師とのコミュニケーションを密に取ることで、愛犬のてんかんを適切に管理し、その生活の質を守っていくことができるでしょう。

よくある質問
1. 犬のてんかんの症状はどのようなものですか?
犬のてんかんには、全身発作と部分発作の2つの主な症状があります。全身発作では筋肉の硬直や全身けいれん、意識消失が見られ、部分発作では特定の体の部位のけいれんや焦点が合わない、口をパクパクさせるなどの症状が現れます。その他にも急な倒れ込みやよだれの増加、落ち着きのなさなどの症状も現れる可能性があります。
2. 発作の前兆や後遺症はどのようなものですか?
発作の前兆としては、攻撃的になったり不安定な行動を示すことがあります。また、発作後にはよろよろした歩行や異常な食欲・水分摂取が観察されることがあります。これらの症状に気づくことで、早期に獣医師に相談することができます。
3. てんかんが起きやすい犬種はどのようなものですか?
ゴールデン・レトリーバー、ラブラドール・レトリーバー、ビーグルなどの犬種はてんかんのリスクが高いと考えられています。これらの犬種は遺伝的な要因が強く関与していると考えられています。また、ストレスの多い環境や急激な気候変化などの環境要因も発作を引き起こしやすくなります。
4. 発作が起きた際にはどのように対応すべきですか?
発作中は周囲の安全を確保し、刺激を避けることが重要です。また、発作の様子を記録しておくと診断の際に役立ちます。発作後は犬の様子を観察し、体温管理に気をつけましょう。特に発作が長引く場合や、意識が戻らない場合は速やかに獣医師に相談する必要があります。

最新記事 by 大森ペット霊堂 (全て見る)
- ノルウェージャンフォレストキャットがかかりやすい病気と健康管理法 - 2025年4月4日
- ビーグルの火葬ガイド:愛犬との最後の別れを大切に - 2025年4月3日
- ペットロス症候群とは?愛するペットの喪失からくる心理的影響を解説 - 2025年4月2日