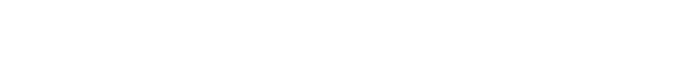2025年版!お焼香のやり方を宗派別に徹底解説
2025年3月16日

仏教儀式におけるお焼香は、故人への敬意と感謝の気持ちを表す大切な行為です。しかし、手順や回数などの作法は宗派によって異なります。このブログでは、お焼香の意味や役割、そして宗派別の作法の違いについて詳しく解説していきます。
目次
1. お焼香の基本的な意味と役割について
お焼香は、仏教の儀式において極めて大切な行為であり、伝統に根ざした深い意味を持っています。この儀式は、故人や仏に対しての心からの敬意を示し、彼らの魂に安らぎを与えることを目的として行われます。お焼香は単なる行動ではなく、故人に思いをしっかり届ける時間です。ここでは、お焼香の意味や役割についてご説明します。
お焼香の目的
お焼香の主要な目的は、以下の三点に要約されます。
- ・故人への供養: 香を焚く行為は故人への供物とされており、彼らの安息を祈る重要な行為です。香の清らかな香りは、故人の霊を導く力を持つと考えられています。
- ・浄化の象徴: 香の煙は、周囲の悪影響を払う力があるとされ、場を清める役割を果たします。このため、お焼香を行うことによって自身の心や体をも浄化することが目的となります。
- ・謙虚と敬意の表現: お焼香は、故人や仏に対して敬虔な心で行われるべき行為です。このプロセスを通じて、参加者の心が自然と仏に向かうことが期待されます。
お焼香の儀式の流れ
お焼香は主に葬儀や法要で行われることが多く、一般的な儀式の流れは次の通りです。
- ・合掌: お焼香を始める前に、故人への感謝の念を込めて合掌をします。
- ・香の燃焼: 抹香や線香を使用して香を焚き、この行為は葬儀の中で思いを込めた重要な部分を占めます。
- ・再合掌: 香を焚いた後、再度合掌し、故人を偲びます。このように、お焼香は連綿とした儀式を通して故人への想いを表現する手段となります。
焼香のタイミング
お焼香は特定のタイミングで行われることが多く、通夜や告別式などの正式な場面で行うことで心の絆がより強まります。お焼香を行う際には、故人への敬愛や感謝の気持ちが大切です。これは単なる儀式にとどまらず、故人との関係を如何に大切にしたいかを示す貴重な機会となります。
お焼香の重要性
お焼香の意味は、個々の宗教観や考え方によって異なる場合もありますが、基本的には「故人を思う心」がすべての基盤となっています。周囲の習慣や形式に流されることなく、真摯な気持ちで行うことが重要です。葬儀や法要の際に、お焼香を通じて自分の気持ちをしっかり伝えることが、故人にとってもありがたい意義を持つのです。

2. お焼香の正しい手順を覚えよう
お焼香は、故人に対する敬意を表し、彼らの冥福を祈るための重要な儀式です。正しい手順を理解することで、参列者としてのマナーを守りつつ、心からの思いを込めてお焼香を行うことができます。それでは、一般的なお焼香のやり方を詳しく見ていきましょう。
基本的な手順
- 1.順番が来たら席を立つ
自分の番が来たら、静かに席を立ち、焼香台に向かう準備をします。 - (大森ペット霊堂の法要では、焼香台が回ってきますので座ったままで大丈夫です。)
- 2.遺影に向かって一礼
焼香台の前に立ったら、改めて遺影に一礼します。この瞬間は、故人を思い出し、敬意を持って接する大切な時間です。 - 3.抹香をつまむ
右手の親指・人差し指・中指を使って抹香を優しくつまみます。この動作は「押しいただく」と呼ばれ、抹香を額の高さまで持ち上げて、心を静めるために深呼吸します。 - 4.香炉へ抹香を落とす
抹香を香炉へ落とします。この際、宗派によってお焼香の回数が異なるため、注意が必要です。例えば、天台宗では1~3回、真言宗では通常3回が一般的です。 - 5.再度一礼
焼香が終わったら、遺影に向かって再び合掌し、一礼します。このとき、故人への感謝や祈りを心に込めましょう。 - 6.席に戻る
遺影に目を向けながら、数歩後退し、遺族に一礼してから自分の席に戻ります。この行動は静かに行うことが求められます。
注意点
- ・宗派による違い
宗派ごとにお焼香の作法や回数には違いがありますので、参加する葬儀がどの宗派に属するのかを事前に確認しておくことが重要です。 - ・座礼焼香や廻し焼香
畳敷きの葬儀会場では、通常座礼焼香が行われ、正座して行動します。また、狭い会場の場合には、参加者が自席に着いたまま焼香器を回す廻し焼香が実施されることもあります。こうした特別な状況でも基本的な流れは変わりません。
焼香の心構え
お焼香はただの形式的な儀式ではなく、故人に対する深い思いを込めた行為です。手順を正確に守ることも大切ですが、最も重要なのは心から故人を偲ぶことです。他の参列者の様子を気にしつつも、落ち着いて行動できるよう心がけましょう。

3. 宗派別のお焼香作法の違いを解説
お焼香は、故人への敬意を表し、感謝の気持ちを示すための大切な儀式です。この作法は宗派ごとに異なり、実施回数や方法にも様々なバリエーションがあります。今回は、主要な宗派ごとのお焼香のやり方について詳しく解説します。
天台宗
- 回数: 一般的には1回から3回行われます。
- 方法: 右手の親指、人差し指、中指を使い、まず抹香をつまんで額の近くで掲げた後、香炉にその抹香をくべます。この際、抹香を高く掲げることが重要なポイントです。
真言宗
- 回数: 通常は3回行うのが一般的です。
- 方法: 右手で抹香をつまみ、同時に左手で支えながら額の高さに持ち上げ、香炉に3回繰り返してくべます。この時、抹香を押しいただくことがポイントになります。
浄土宗
- 回数: 特に決まった回数は設けられていませんが、一般的には1回から3回が多いです。
- 方法: 右手の3指で抹香をつまみ、左手を添えて額まで持ち上げた後、香炉にくべるというスタイルです。
浄土真宗
- 本願寺派
- 回数: 1回が基本です。
- 方法: 抹香を押しいただくことはせず、直接香炉にくべる方法です。
- 大谷派
- 回数: 2回が標準です。
- 方法: 本願寺派同様に、抹香を押しいただくことなく香炉にくべます。
臨済宗
- 回数: 基本的には1回です。
- 方法: 押しいただくかどうかは各宗寺によって異なる場合がありますが、一般的には右手の3指で抹香を押さえ、それを香炉にくべるのが普及しています。
曹洞宗
- 回数: 多くの場合、2回行われます。
- 方法: 最初の1回目は、右手の3指で抹香をつまみ、額の高さに掲げてから香炉にくべます。2回目は、抹香を押しいただかずにくべるスタイルが一般的です。
日蓮宗
- 回数: 僧侶が3回行う一方で、一般の参列者は1回または3回の中から選択できます。
- 方法: 右手の親指と人差し指で抹香をつまみ、静かに香炉にくべることが大切です。
お焼香のやり方は宗派毎に異なり、故人やその家族に合わせた宗派を考慮することが必要です。また、地域によって微細な違いがあるため、初めてお焼香を行う場合は周囲の参加者や喪主に確認することをお勧めします。各宗派の独自の作法が存在しますが、心を込めて行う姿勢が最も大切です。

4. 初めての方でも安心!一般焼香のやり方
お焼香は、葬儀や法事において極めて重要な儀礼です。初めて経験する方にとって、その流れや手続きに戸惑うこともあるでしょう。本セクションでは、一般焼香の基本的な手順を分かりやすく解説します。
一般焼香の基本手順
一般焼香は、以下のステップに従って実施します。
- 1.焼香の順番が来たら、焼香台へ向かう – 係の方の指示に従い、丁寧に進みましょう。このとき、数珠は左手で持ち、房部分が下を向くように整えてください。
- 2.故人の遺影、喪主、参列者に敬礼する – 初めに故人の遺影に向かって頭を下げ、その後に喪主へ、最後に周囲の参加者全員にもう一度頭を下げます。
- 3.祭壇上の遺影に対して合掌(または一礼)する – 故人への感謝の思いを込めて合掌するか、一礼を行います。
- 4.抹香をつまみ上げる – 右手の親指、人差し指、中指の3本を使い抹香をつまみ、額の高さに掲げます。
- 香炉への捧げ方 – 抹香を香炉へ静かに落とします。宗派によって焼香の回数は異なりますが、通常は3回行われることが一般的です。
- 5.再度、遺影に合掌(または一礼)を行う – 焼香が終わった後、もう一度故人に感謝の気持ちを込めて合掌します。
- 6.2~3歩下がりながら、喪主と参列者に一礼する – 焼香後は少し後退しつつ、周囲の方々に一礼してから席に戻ります。
注意点
お焼香を行う際には、いくつかの重要なポイントに留意することが求められます。
- ・数珠の持ち方の注意: 数珠は基本的に左手に持ち、房が下を向くように整理しておきましょう。
- ・お辞儀の向きについて: お辞儀をする際には、故人や喪主にしっかりと向き合い、礼をすることが重要です。不適切な方向にお辞儀をしないよう、気を付けてください。
- ・心を込めた行動を: お焼香は形式的なものではなく、心を込めて行うことが大切です。作法を理解した上で、敬意を持って故人を偲びましょう。
一般焼香のやり方をしっかりと理解することで、葬儀や法事に安心して参加できるようになります。大切なのは、正しい作法に従い、真摯な祈りを捧げることです。

5. お焼香の回数に込められた意味を知ろう
お焼香を行う際の香を供える回数には、実は深い意味合いが潜んでいることをご存知ですか?この回数は宗派によって異なる解釈が存在しますが、共通した意味もあります。お焼香の回数の意味を理解することで、心を込めたお焼香ができるようになります。
回数による意味の解説
- ・1回の場合
一度の焼香は「一に還る」とする仏教の教えを意味しています。これは、全ての生命が一つの存在に戻るという思想を表しており、故人への祈りを込めた行為なのです。 - ・2回の場合
二度の焼香は、「主香」と「従香」という二つの側面があります。最初の焼香は故人を思ってのもので、二回目はその香りが消えないようにとの願いを込めています。この二度の儀式を通じて、故人への深い敬意を示し、弔いの気持ちを強調することができます。 - ・3回の場合
三回の焼香は、仏教において「三」という数字が特に重要であることから、三つの宝(仏、法、僧)に祈りを捧げる意味を持ちます。これにより、故人の供養を強化する意義も含まれています。
宗派による違い
お焼香の回数は、宗派によって異なる解釈や実践があります。以下に代表的な宗派の一般的な焼香の回数を示します。
- ・浄土宗: 回数にこだわらず、心を込めて行うことが重視されます。
- ・真言宗: 通常、三回が基本とされており、その回数には特別な意味が与えられています。
- ・曹洞宗: 二回の焼香が一般的であり、主香と従香の思想が大切にされています。
意味を込めた焼香の実践
お焼香の際に行う回数は重要ですが、最も大切なのはその「心」です。たとえ一回でも、心を込めて行うことが大切です。また、周囲の状況に応じて行動することもありますが、最終的には故人を偲ぶ気持ちが反映される瞬間となるでしょう。
お焼香の回数は、その背後にある意味を深める要素です。参列者としての心構えや弔いの姿勢を築くための重要な部分を占めています。信仰や習慣を超えて、心豊かなお焼香を意識することで、より深い祈りを捧げることができるでしょう。

まとめ
お焼香は単なる形式的な行為ではなく、故人への深い敬意と愛情を表す重要な儀式です。回数によってさまざまな意味が込められていますが、何より参列者の心から湧き出る思いが大切です。正しい作法を身につけ、宗派や状況に応じて適切に行動することで、故人の冥福を心から祈ることができるでしょう。お焼香は単なる習慣ではなく、故人を偲び、供養する心の表れなのです。

よくある質問
お焼香の主な目的は何ですか?
お焼香の主要な目的は、故人への供養、浄化の象徴、敬虔な心の表現の3点にあります。故人の霊を導き、周囲の悪影響を払い、故人や仏に対する深い敬意を示すことが目的とされています。
お焼香の正しい手順を教えてください。
お焼香の基本的な手順は、1.順番が来たら席を立つ、2.遺族への一礼、3.遺影に向かって一礼、4.抹香をつまむ、5.香炉へ抹香を落とす、6.再度一礼、7.席に戻るです。宗派によって多少の違いがあるため、参加する葬儀の宗派を確認しましょう。
宗派によってお焼香の作法は異なるのですか?
はい、お焼香の回数や方法は宗派によって異なります。例えば、天台宗は1~3回、真言宗は通常3回、浄土宗は1~3回など、様々な違いがあります。地域や寺院によっても細かな差異があるため、状況に応じて確認することが大切です。
初めてお焼香する場合、気をつけることはありますか?
初めての方でも安心して参加できるよう、一般的な焼香の流れを理解することが重要です。焼香台に向かう際の動作、遺影や喪主への敬礼、抹香の上げ方、香炉への捧げ方など、丁寧に行動することが求められます。慣れない場合でも、周囲の様子を参考にしながら、心を込めて行うことが最も大切です。

最新記事 by 大森ペット霊堂 (全て見る)
- ペットロス症候群とは?愛するペットの喪失からくる心理的影響を解説 - 2025年4月2日
- コーギーの平均寿命を延ばすための健康管理と飼育のコツ - 2025年4月1日
- 【4月合同法要】日程のお知らせ - 2025年4月1日